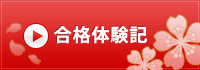現役合格おめでとう!!
2025年 三軒茶屋校 合格体験記

早稲田大学
先進理工学部
応用化学科
井口遥人 くん
( 世田谷学園高等学校 )
2025年 現役合格
先進理工学部
僕が東進に入学したのは高2の頭でした。当時は受験に対する意識が芽生えてなく、志望校合格のためにやらなければならないことを告げられた時は驚愕でした。最初は担任助手の方に言われるがままに受講を進めていたのですが、あまり成績が上がらず焦りを感じていました。主体的に学習に取り組むようになったのはそのころからだと思います。担任の先生・担任助手の方に自分の意見をぶつけて志望校合格への最短距離を模索し、それを実行しました。
東進に通えるという恵まれた環境にいる皆さんが合格に必要なのはやる気だけです。僕は結果として指定校推薦という形で受験の幕を閉じましたが、そうでなくても難関大学に合格したであろうという自信があります。それは東進での話し合いにて決めたルートにのっとり着実に成績を伸ばしていたからです。皆さんもやると決めたことに手を抜かずに真摯に取り組むことで確実に第一志望合格に近づけると思います。
ここで具体的なおすすめの数学の勉強法を紹介します。それは各共通テスト本番レベル模試に向けて単元をいくつか決めて問題集などを用いてほぼ満点がとれるようにすることです。国公立や共通テスト利用を考えている人は共通テストを解けるようにすることは必須ですし、現在の共通テストのレベルは高いので私大の入試問題の橋渡しにもなります。僕も実際にこの方法で共通テストの練習問題では9割越えを安定してとれるようになりましたし、入試演習が始まってからも戦うことができました。何より1つ1つの目標の期限が短いので取り組みやすいです。最後になりますが、私は就職という1つの目標に向けて頑張りたいと考えているので皆さんも受験勉強頑張って下さい。
東進に通えるという恵まれた環境にいる皆さんが合格に必要なのはやる気だけです。僕は結果として指定校推薦という形で受験の幕を閉じましたが、そうでなくても難関大学に合格したであろうという自信があります。それは東進での話し合いにて決めたルートにのっとり着実に成績を伸ばしていたからです。皆さんもやると決めたことに手を抜かずに真摯に取り組むことで確実に第一志望合格に近づけると思います。
ここで具体的なおすすめの数学の勉強法を紹介します。それは各共通テスト本番レベル模試に向けて単元をいくつか決めて問題集などを用いてほぼ満点がとれるようにすることです。国公立や共通テスト利用を考えている人は共通テストを解けるようにすることは必須ですし、現在の共通テストのレベルは高いので私大の入試問題の橋渡しにもなります。僕も実際にこの方法で共通テストの練習問題では9割越えを安定してとれるようになりましたし、入試演習が始まってからも戦うことができました。何より1つ1つの目標の期限が短いので取り組みやすいです。最後になりますが、私は就職という1つの目標に向けて頑張りたいと考えているので皆さんも受験勉強頑張って下さい。

早稲田大学
教育学部
教育学科/教育学専攻/教育学専修
酒匂美奈 さん
( 新宿高等学校 )
2025年 現役合格
教育学部
私は2年生の夏頃に東進に入学しました。その頃は学校生活が忙しくてあまり東進に行けてなかったです。受験が終わった今でも、その頃のことを少し後悔しています。東進ではよく言われる通り、早い段階からしっかり勉強している人は絶対に結果がついてくると思います。まだまだ受験当日まですごく長いなと思っていたらすぐに受験期の終わりのほうまで来てしまっていたという印象が大きいです。
しかし私が焦りながらも頑張れたのは、私のことを信じて応援してくれる担任助手の方々がいたからだと思います。たくさん頼らせてもらって、1人ひとりに本当に感謝しかないです。受験生は溜め込まず周りの人にたくさん相談して、受験に関して知識をつけるべきだと思います。受験は情報戦でもあるし、話すだけでも不安は和らぎます。死ぬほど頑張っても受験当日はなにがあるかわからないし、報われるとは限りません。秋ぐらいはそういう考えがずっと頭にあって、不安で勉強に集中できませんでした。でも年末あたりで、そんなこと考える暇なくただ勉強すればいい!!と思ってからは自分のやるべきことが見えてきて集中できるようになったと思います。
受験が終わっていろんな思いがあるけど、東進で勉強できて本当によかったと思っています。
しかし私が焦りながらも頑張れたのは、私のことを信じて応援してくれる担任助手の方々がいたからだと思います。たくさん頼らせてもらって、1人ひとりに本当に感謝しかないです。受験生は溜め込まず周りの人にたくさん相談して、受験に関して知識をつけるべきだと思います。受験は情報戦でもあるし、話すだけでも不安は和らぎます。死ぬほど頑張っても受験当日はなにがあるかわからないし、報われるとは限りません。秋ぐらいはそういう考えがずっと頭にあって、不安で勉強に集中できませんでした。でも年末あたりで、そんなこと考える暇なくただ勉強すればいい!!と思ってからは自分のやるべきことが見えてきて集中できるようになったと思います。
受験が終わっていろんな思いがあるけど、東進で勉強できて本当によかったと思っています。

早稲田大学
社会科学部
社会科学科
野村秀丞 くん
( 世田谷学園高等学校 )
2025年 現役合格
社会科学部
僕が東進に入学したのは高2の3月でした。それまでは家で勉強していましたが、1人で勉強し続けることに限界を感じたため、映像による授業で自分のペースで学習を進められる東進を選びました。
夏までに自分の苦手をつぶすことに注力したことで秋以降の過去問演習にスムーズに入ることができ、また志望校別単元ジャンル演習講座で繰り返し演習することによって、受講した内容を定着させることができました。とにかく大量の演習をしたことによって秋以降飛躍的に英語力がつき、それが早稲田大学の合格につながったと思います。高2の1月には解き終わることすらできなかった英語リーディングは模試を追うごとに点数が上がっていき、本番では9割とることができました。また1番苦手な国語は模試でも7割を超えることはほとんどなく、不安材料でしたが、ぎりぎりまで諦めずに演習を続けたことで本番では167点を取ることができました。
また志望校別単元ジャンル演習講座は、「受講→その範囲を演習」のような形で進めていました。せっかく受講して学力をつけても演習しなかった、という失敗を夏前に犯してしまったので、このような形をとりました。とにかく自分に合った学習を見つけることが1番だと思います。自分の将来のためにこれほど努力できる時期はなかなかありません。
みなさんも目標を見つけ、それに向かってひたすら努力を続ければ、合格をつかみ取ることができると思います。応援しています。
夏までに自分の苦手をつぶすことに注力したことで秋以降の過去問演習にスムーズに入ることができ、また志望校別単元ジャンル演習講座で繰り返し演習することによって、受講した内容を定着させることができました。とにかく大量の演習をしたことによって秋以降飛躍的に英語力がつき、それが早稲田大学の合格につながったと思います。高2の1月には解き終わることすらできなかった英語リーディングは模試を追うごとに点数が上がっていき、本番では9割とることができました。また1番苦手な国語は模試でも7割を超えることはほとんどなく、不安材料でしたが、ぎりぎりまで諦めずに演習を続けたことで本番では167点を取ることができました。
また志望校別単元ジャンル演習講座は、「受講→その範囲を演習」のような形で進めていました。せっかく受講して学力をつけても演習しなかった、という失敗を夏前に犯してしまったので、このような形をとりました。とにかく自分に合った学習を見つけることが1番だと思います。自分の将来のためにこれほど努力できる時期はなかなかありません。
みなさんも目標を見つけ、それに向かってひたすら努力を続ければ、合格をつかみ取ることができると思います。応援しています。

慶應義塾大学
文学部
人文社会学科
島田健太郎 くん
( 佼成学園高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
僕は高校2年生のころに東進三軒茶屋校に入学しました。入学した理由は、学校が近い校舎ではなく自宅に近い校舎を選ぶことで学校の友達との喋り時間を削り、勉強に集中できることや自分のペースで勉強を進められるカリキュラムだったからです。入学したころは、高校2年生の10月まで野球をしていて勉強に触れていなかったので偏差値も30近く、慶應義塾大学合格は夢のまた夢でした。しかし、友人が慶應で活躍している姿を見て憧れを抱き、また兄弟で慶応に合格するという思いから1度も諦めることなく勉強を続けたことが合格につながりました。
合格に向けて勉強する中でおすすめの東進コンテンツが3つあります。1つめがチームミーティングです。チームミーティングをただの計画立ての時間に使わず、友達と苦手分野の勉強法を共有するなどコミュニケーションをとることがおすすめです。2つめは志望校別単元ジャンル演習講座です。自分の苦手な範囲だけではなく、苦手と気づいていなかった範囲まで網羅して勉強できるところや、問題がたくさんあり何を勉強すればいいか悩まなくなるので、無駄な時間を省けられます。3つめは自分のペースで勉強できるところです。担任の先生と長期・中期の勉強計画を立て、担任助手の方と短期的な計画を個々のペースで立て勉強できます。
僕は東進でなければ現役で慶應義塾大学に合格できなかったと思います。それは勉強での悩み事を気軽に聞ける環境が整っていたので、気持ちの浮き沈みに大きな差がなく平常心で1年間勉強を継続できたからです。人と話すのが好きな僕は、年の近い担任助手の方や担任の先生との会話が心の支えでした。将来は長所であるコミュニケーション能力を生かして、視野を広く持ち周りの人をマネジメントするとともに営業職として人の心を動かしたいです。受験勉強で大切なのは精神力です。常にポジティブに前向きに勉強を継続すればどんな目標でも達成できます。自分を信じ、周りの人の支えに感謝し、高校生らしくがむしゃらに夢に向かって頑張ってください。応援しています!
合格に向けて勉強する中でおすすめの東進コンテンツが3つあります。1つめがチームミーティングです。チームミーティングをただの計画立ての時間に使わず、友達と苦手分野の勉強法を共有するなどコミュニケーションをとることがおすすめです。2つめは志望校別単元ジャンル演習講座です。自分の苦手な範囲だけではなく、苦手と気づいていなかった範囲まで網羅して勉強できるところや、問題がたくさんあり何を勉強すればいいか悩まなくなるので、無駄な時間を省けられます。3つめは自分のペースで勉強できるところです。担任の先生と長期・中期の勉強計画を立て、担任助手の方と短期的な計画を個々のペースで立て勉強できます。
僕は東進でなければ現役で慶應義塾大学に合格できなかったと思います。それは勉強での悩み事を気軽に聞ける環境が整っていたので、気持ちの浮き沈みに大きな差がなく平常心で1年間勉強を継続できたからです。人と話すのが好きな僕は、年の近い担任助手の方や担任の先生との会話が心の支えでした。将来は長所であるコミュニケーション能力を生かして、視野を広く持ち周りの人をマネジメントするとともに営業職として人の心を動かしたいです。受験勉強で大切なのは精神力です。常にポジティブに前向きに勉強を継続すればどんな目標でも達成できます。自分を信じ、周りの人の支えに感謝し、高校生らしくがむしゃらに夢に向かって頑張ってください。応援しています!

東京学芸大学
教育学部
学校教育教員養成課程/養護教育専攻(D類)
岩垂愛花 さん
( 西高等学校 )
2025年 現役合格
教育学部
私が東京学芸大学に合格をいただくことができたのは受験勉強をする中で絶えず自己分析を続けたこと、これに加え東進に通っていたことでそれを活かした勉強をすることができたことが大きな理由だと思います。
私は高校までずっと公立に通っており、東進に入学した2年の2月時点で、いわゆる私立の先取り勉強をしている人とは大きな差があると強く感じていました。どうやってこの差を埋め戦っていくかと考え出た結論は、残っている時間を無駄にせず自分ができる最高効率で学んでいく必要があるということでした。この考えのもと本格的に勉強を始めた4月から受験までの1年間の計画をざっくりと立て、毎月現時点での弱点とやるべきことの優先順位を考えるようにしていました。
このような勉強方法を取っていた私にとって非常にありがたかったものが、東進の完全な映像による授業の形式と毎月行われる模試です。もちろん担任の先生からの指導もありますが、自分のペースで授業を受けられることで苦手科目はじっくりと、得意科目はガツガツと進めていくことができました。また模試を受けることで主観だけでなく客観的な分析もして計画をたてられたと思います。
話は変わりますが、わたしは高校3年生の夏終わりに大きく志望校を変更する決断をしました。夏休みに学びを深め様々な壁に当たり自分を見つめなおしたときに私がやりたいことはなにかに気づくことができたからです。しかし、きっと2年の終わりにもこのことには気づくことができたと思います。受験直前で志望校を変えることは応援してくれていた親にも大きな心配をかけてしまい、悔いのない決断ができた反面大きな後悔でもあります。みなさんには志望校を決める段階から深く自分のやりたいことを考えてほしいですし、悔いのない選択、勉強をしてほしいと思っています。
私は高校までずっと公立に通っており、東進に入学した2年の2月時点で、いわゆる私立の先取り勉強をしている人とは大きな差があると強く感じていました。どうやってこの差を埋め戦っていくかと考え出た結論は、残っている時間を無駄にせず自分ができる最高効率で学んでいく必要があるということでした。この考えのもと本格的に勉強を始めた4月から受験までの1年間の計画をざっくりと立て、毎月現時点での弱点とやるべきことの優先順位を考えるようにしていました。
このような勉強方法を取っていた私にとって非常にありがたかったものが、東進の完全な映像による授業の形式と毎月行われる模試です。もちろん担任の先生からの指導もありますが、自分のペースで授業を受けられることで苦手科目はじっくりと、得意科目はガツガツと進めていくことができました。また模試を受けることで主観だけでなく客観的な分析もして計画をたてられたと思います。
話は変わりますが、わたしは高校3年生の夏終わりに大きく志望校を変更する決断をしました。夏休みに学びを深め様々な壁に当たり自分を見つめなおしたときに私がやりたいことはなにかに気づくことができたからです。しかし、きっと2年の終わりにもこのことには気づくことができたと思います。受験直前で志望校を変えることは応援してくれていた親にも大きな心配をかけてしまい、悔いのない決断ができた反面大きな後悔でもあります。みなさんには志望校を決める段階から深く自分のやりたいことを考えてほしいですし、悔いのない選択、勉強をしてほしいと思っています。